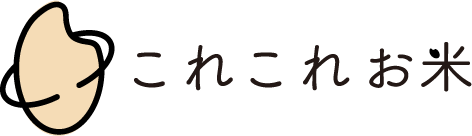そんなお話。

大転換をむかえた日本の稲作に世界が期待している
1960年代から、主食用の米の消費量は減少傾向にあり、近年では年に8万~10万トンのペースで減少しています。これは日本全体の米生産量の1%以上で、小さな県の年間生産量にも匹敵します。加えて、少子化で日本の人口が減りはじめていることから、日本人がお米を食べる量もさらに減っていくことが予想されます。一方で米の生産現場では高齢化が進んでいますが、70歳以上になって引退する農業従事者が増える一方で、担い手も減少の一途をたどっています。このように米の消費と、お米の作り手の双方が減っていく中、今後農業技術として何を目指さなければならないのか、国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構の坂井真先生にお話を伺いました。
小規模稲作からメガファームの時代へ、国内消費主体から輸出開拓へ
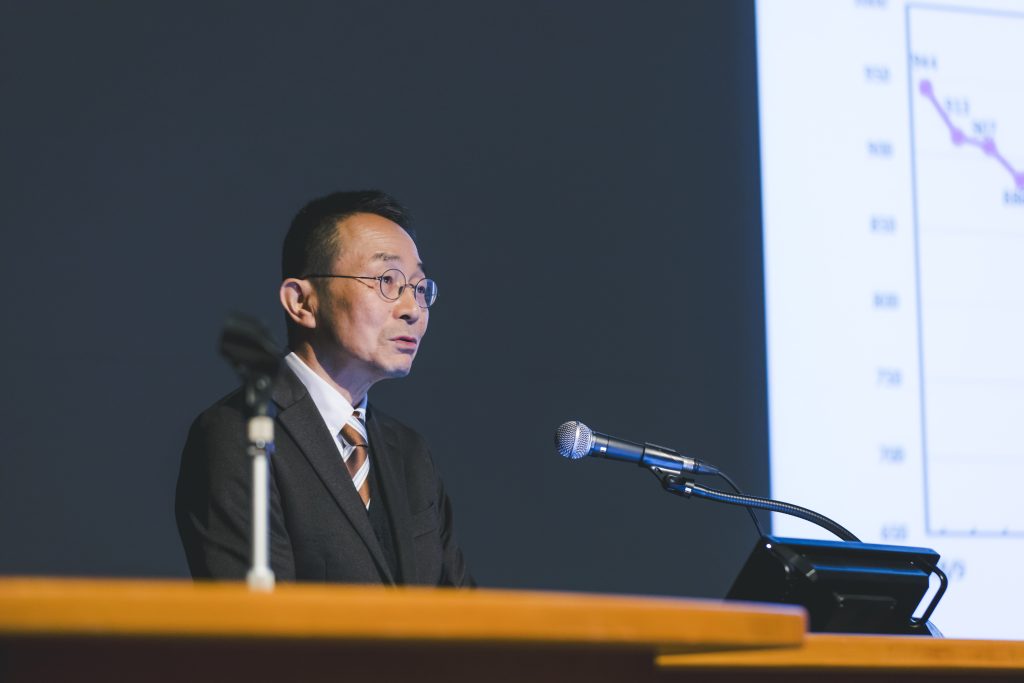
農林水産省の「農業センサス」から経営規模別の農業経営体数を見ると、近年10ヘクタール未満の経営体が大きく減少しています。一方、10ヘクタール以上の大規模な経営体は増加しており、特に増加が目立つのが50ヘクタール、あるいは100ヘクタール以上の経営体です。つまり、小規模な農家が減って大規模な農業法人が増えています。私が就職した1980年代には、農業経営の専門研究者から「農家ごとの中型コンバインと田植え機の装備で1軒の農家が経営できる面積は、20ヘクタールが限界ではないか」と聞かされました。長い間それが常識だと思っていたのですが、現在は100ヘクタール以上のメガファーマーが稲作を担うのが当たり前になっています。今後も小規模な農家が自ら耕作することをやめて、大規模な農業法人に農地を預けることで、作付けが集中する農業法人が地域の稲作を支えていく状況がさらに進むと思われます。
一方、輸出に目を向けると、日本からの米やその製品の輸出は着実に伸びています。2014年には米の輸出は4000トンほどしかなかったのですが、2022年は2万9000トン、2023年は3万トンを超えそうな勢いです。輸出先としては、これまでは香港、シンガポール、台湾が中心でしたが、最近ではアメリカが増えています。その理由としては日本食レストランが海外で増えていることが考えられます。近年、日系の中食・外食チェーンが数多く海外に進出しています。これまで世界の人々には、日本の米のおいしさが知られていませんでしたが、それを知らしめる環境が整いつつあります。ただ、米は世界的に見て非常に貿易量の少ない作物で、その中でも日本産米に近い品質のジャポニカ米の貿易量は100万トン程度にすぎません。また、そのほとんどが、アメリカのカリフォルニア産で占められているのが現状ですが、その中でどれだけシェアを取っていけるかが今後の課題になると思っています。
現代の日本では少子高齢化が進み、単身世帯や核家族が増えています。そうなると、消費者があまり家でご飯を炊かなくなっていき、外食・中食でという傾向が強まり、米ではなくお弁当や冷凍米飯、パックご飯など、「ご飯」のかたちで流通する量がさらに増えると思われます。それから、上で述べたように農業従事者数が減って、大規模経営体が増加していくわけですが、そうなるとこれまでよりも農作業の手間のかからない稲作技術が求められるようになります。また、世界に目を向けるとアジア・アフリカ諸国の経済発展に伴い、富裕層、中間層が求めるおいしくて高品質な食材としての日本食、日本米、日本酒などのニーズは増えていくでしょう。これらの流れをどのようにキャッチアップしていくかが、これからのわが国の稲作の大きなテーマだと考えています。
進化した稲作技術で生産性の向上を
最近の稲作技術をみると、品種改良の面ではゲノム情報を活用した育種や野生種からの有用な形質の活用が可能になり、これまでにない多様なタイプの品種が開発されてきています。栽培管理の面では、いわゆる「スマート農業技術」として、自動運転農機やリモートセンシングで圃場や生育の状況を把握できる技術の開発が進んでいます。食品加工技術面では米をこれまでと違った用途で活用する技術が生まれてきています。国内の米飯消費は減っていますが、米粉用等や製品も含めた輸出のニーズは増えているので、そうしたことも合わせて考えると、加工適性や業務用途、輸出用途それぞれに応じた品種とそれを低コストで生産できる栽培体系が求められます。
経営の大規模化が進んでいくと、一つの経営体の中でも作期の幅が広くなってきます。そうなると、刈り取り適期が長く省力化できる品種や技術が求められます。それに対応した技術としては、直播栽培やスマート農業の技術があげられます。これまでは水田に田植え機を使って苗を植えるのが当たり前だったのですが、それに対して直播栽培では水田に直接種をまくことで育苗や苗を運搬するコストを大きく抑えることができます。例えば、100ヘクタールの水田に田植えをするには苗箱約2万枚分の苗を育てて準備する必要がありましたが、直播栽培ではそれが不要になるのです。この15年で田植えをしない直播栽培の面積は2.5倍になりました。10アールあたりの労働時間がこれまで移植栽培で18時間かかっていたものが直播栽培だと14時間になるというデータも公表されています。ただし、現在の品種を用いた直播技術では労働時間や生産コストが少なくなる反面、収量が少し下がってしまうことが多く、改善の余地があります。もし、この収量の課題が解決できれば、直播はこれまでの移植栽培に取って代わる生産性向上技術になる可能性があります。
地球温暖化に耐えうる新しい品種に期待が集まっている

地球温暖化の影響とみられる、夏季の高温による稲作への影響が昨今よく報道されています。2023年の夏は非常に暑かったので、一等米比率が9月30日時点で過去最低の59.6%(月現在)となり、「災害級との声もある」という報道もなされていました。これまで日本では暑い日照りの夏でも、干ばつにならなければお米は豊作といわれていたのですが、2000年代以降稲の実る時期に高温になり過ぎて、米の品質が低下することが各地で報告されており、その対策技術が求められています。その地球温暖化に適応した先駆的な品種として「にじのきらめき」があります。これは2019年に品種登録出願された新しい品種です。コシヒカリに比べて、明らかに高温に強いことに加えて、倒れにくく収量が15%から30%ほどたくさん取れて、病気にも強いという、いいとこ取りの品種で、いま北陸地域から関東地域で急速に作付けが伸びています。そして、もう一つ注目すべき品種として富山県と農研機構が共同育成した「富富富(ふふふ)」があります。これは最新のDNAマーカーを使ったゲノム育種により育成された品種で、倒れにくいコシヒカリと病気に強いコシヒカリと高温に強いコシヒカリをそれぞれ作り、それらのメリットを全部合わせもつようにした品種です。「富富富」は2023年には富山県のコシヒカリの一等米が45%しかない中、90%以上の一等米比率という驚異的なスペックを示し、富山県内では「もっと生産を拡大してほしい」という要望も出ている品種です。今後、高温に強い品種の開発はますます加速する
ことが見込まれます。
米粉用専用品種と製粉技術の進化で新しい用途に対応
伝統的な日本の米粉には、上新粉や道明寺粉などがあります。これらは和菓子、とりわけ餅菓子や水菓子のようにもっちりと粘りのある食感を作るのに使われてきました。これに対して、新しいタイプの米粉として、パンやケーキ、焼き菓子などの洋菓子に対応したタイプの米粉が開発されています。これは、製粉技術と品種開発の両方面からの取り組みで実現したものです。今から15年ほど前、米粉用の品種開発を私たちが開発をはじめた頃、米粉はマイナーな存在だったのですが、現在は米粉の年間消費量は4万トンにまで増加しています。当初よりずいぶん増えてはいるのですが、まだ主食用米生産量の1%以下で、もっと増える余地はあると思っていますが、それでも、うるち米や、もち米、酒造好適米に続く第4の米の用途として、しっかりした存在感を示しつつあります。近年、開発された米粉専用の品種の「ミズホチカラ」やその改良版の「笑みたわわ」の米粉は、グルテンを添加しなくてもパンを焼くことができ、しかも生地がよく膨らむという特性を持っています。その理由として、粉にするときのでんぷんの損傷が少ない、米粉の粒が細かくひける、などこれまでの主食用米にない特性を持っていることが明らかになりつつあり、今後一層の利用拡大が期待されます。
視点を変えると、日本の稲作の未来は明るい
現在、日本の稲作と米は変革期にあると私は思っています。国内消費の長期低迷と生産基盤の弱体化が相まって、一見して日本の稲作はピンチにあるように見えます。しかし、大規模な農業法人(メガファーム)が台頭し生産性の高い稲作に取り組んでいます。一方、中食・外食の業務用・加工用需要は増えており、流通企業や実需が直接関わることで集荷や流通も変わりつつあり、コシヒカリ一辺倒のブランド神話も薄れつつあります。また調理用や米粉利用といった新しいニーズの拡大も見込めますし、そうした製品を海外に販路も求めていくことも期待されます。かたや生産の不安定要因として、夏の高温による産米の品質低下や収量の減少への対策や、さらには水田から発生する温室効果ガスの低減が求められていますが、これらの対策としては品種面の対応など対策技術が開発されつつあります。これからは、新しい技術をうまく使いながら、新しい時代に合った稲作、そして低コストで安定していて、環境負荷の少ない生産技術を確立することが稲作の明るい将来につながるのではないかと考えます。
〈プロフィール〉
坂井 真(さかい まこと)
京都大学農学部卒業。農学博士。1985年農林水産省入省。以後品種改良の専門家として4か所の育種試験地で28年間従事。50品種以上のイネ品種開発に関与(「にこまる」「きぬむすめ」「あきだわら」「ミズホチカラ」「吟のさと」等)。その後、技術キャリアを持つ産学官連携担当として農研機構の技術普及に尽力し、高温に強い稲「にこまる」の普及拡大に貢献、多収米、米粉パン用米、酒造好適米、紫黒米、低アミロース米(+冷凍すし製品)等の用途開発と普及を公設試、民間企業等との協働で多数実現。2014年3月には日本育種学会賞を受賞。
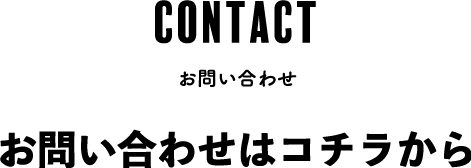 メールからのお問い合わせ
メールからのお問い合わせ